このページは旧ページです。新ページをご利用下さい。
市場魚貝類図鑑では現在新ページへの移行を行っております。
既に一部のページを除き、新ページの方が内容が充実しております。新ページも合わせてご利用下さい。
新ページ「マボヤ」はこちら >>
|
|
|
◆食べてみる◆
食べ方はホヤの岩などについている方を切り、まず体内の海水をボウルに受ける。そして二つ割、皮を剥いだら内側の黒い部分や透明なワタを出し、刺身にきる。これを取り出した水とともに提供する。これが一番うまい。物足りないと感じたら塩でたべるのががよい。
岩手などでは酢の物が定番となっている。キュウリと合わせて二杯酢。
ホヤはほとんど生で食べられるのだが、三陸では焼いて食べる。焼くと渋みも旨味も濃厚になり、独特の風味が増す。。
また茹でるというのが甲斐崎圭という人の本にあった。ホヤを2つ割にして塩と七味唐辛子で下味をつけておく、これを茹であげるのだ。これは料理として確立しているもの。ホヤの海味が凝縮していて過激に舌を刺激する。
ほかに定番なのは塩辛。レモンなどの柑橘類と合わせるとうまい。
このホヤにこのわた(ナマコの内臓の塩辛)を合わせたものが莫久来(ばくらい)というのがあるが、これは非常に美味。
珍しいものに三陸でからからに干したものが売られているが、これなど海の味のチップスとも言えそう。
●広島県倉橋島の「日美丸」さんのページにあるのでご覧頂きたい
http://ww5.enjoy.ne.jp/~kogera0401/
●寿司に関しては寿司図鑑へ!
●参考文献/『原色日本海岸動物図鑑』(内海富士夫 保育社)、『新北のさかなたち』(水島敏博、鳥澤雅他 北海道新聞社)、『聞き書 岩手の食事』(農文協)、『たべもの語源辞典』(清水桂一編 東京堂出版)、『青森県 さかな博物誌』(日下部元慰智 東奥日報社)、『新版 水産動物学』(谷田専治 恒星社厚生閣)、『比較動物学 アメーバからヒトまで』(M.フィンガーマン 培風館)、広辞苑
■市場魚貝類図鑑データベースから
■がついたものは引用部、もしくは参考文献あり
●本サイトの無断転載、使用を禁止する
|
|
|
|
 |
 |
 |
形態◆赤く強い皮に包まれ、無数の角状の突起のあるイボがある。身体の上部には入水管、出水管がある。出水管は-形、入水管は+形をしてる(画像中)。養殖ものは赤が強く、天然ものは薄い。瀬戸内海などには真っ白い個体(画像いちばん下 広島県倉橋島日美丸さんから)がいる。
|
|
脊索動物門尾索動物亜門海鞘綱(ホヤ綱)
|
|
壁性目(側性ホヤ目)褶鰓亜目ピウラ科(マボヤ科)
|
|
|
|
魚貝の物知り度/★★★ 知っていたら通人級
食べ方◆生(刺身、酢の物)/ゆでる/焼く/干す
◎非常に美味だが好みが分かれやすい
|
大きさ◆■体長20センチを超える
|
| 生息域◆■北海道以南。山東半島、朝鮮半島。牡鹿半島、男鹿半島以北に多い。 |
生態◆
■産卵期は秋から冬、春。
■岩や貝などに付着。
|
ホヤについて◆
■殻皮(皮嚢)または外套膜という丈夫な膜で包まれているので「皮嚢類」とも。
■脊索動物門尾索亜門で人、魚、カエルなどの脊椎動物亜門と「門(分類のもっとも上位)」を同じくする。
■脊索動物門頭索動物亜門にナメクジウオ。
■入水管と出水管を持ち、入水管で水中の微少なプランクトンなどを摂取、出水管でこした海水や排泄物を出す。
■雌雄同体。
■幼生期にはオタマジャクシに似た形態をしていて(オタマジャクシ幼生)、脊索がある。その後付着生活に入る。
■食用となるのは国内ではマボヤ、アカボヤ。韓国などではエボヤ、シロボヤ(?)。 |
市場での評価・取り扱われ方◆
■宮城県、岩手県などで養殖が行われていて年間を通して入荷の多いもの。天然ものはやや少ない。皮をむいて海水と一緒に袋詰めされたものと、活けのものがある。養殖もので1個卸売り価格で100円前後。天然もので200円ほど。 |
マボヤの基本◆
■加工品に干物、塩辛、燻製、ゆでホヤ。
■東北太平洋側青森県、岩手県、宮城県などで主に養殖、採取されている。
■出荷までは4年かかる。
■明治時代、宮城県気仙沼で船のイカリ綱に使っていたヤマブドウの蔓についたマボヤを採取したのが養殖の始まり。
■年間約1万トン、8割前後が宮城県で、2割前後が岩手県産。
■マボヤを食べる習慣があったのは東北太平洋側、青森県、岩手県、宮城県。
■「ホヤを食べて水を飲むとたいへんうまい」といわれる。
■「海のパイナップル」と呼ばれた。
■「藤の花が咲くとホヤがうまくなる」といわれる。
■「海延喜式に胎貝(イガイ)と保夜(ホヤ)のすしがある。これは乳酸発酵させた「なれずし」。
■岩手県釜石市生まれの方に「子供の頃には、ホヤの皮をチュウインガムのように噛んだ」という話を聞いた。このようなマボヤに関する情報がありましたらメールでお知らせください。
■愛知県三河湾では冬に底引き網の副産物として漁獲される。
|
漁獲方法◆養殖/潜水漁
|
漢字◆■「海鞘」、「老海鼠」、「保夜」。
由来◆
■炎のように赤い色をしているから「火焼け(ホヤ)」。
■ほや(宿り木)が根を張るに似ているから。 |
| 呼び名・方言◆■アイヌ語で「トツイ」。 |
| 釣り◆釣り物として紹介するのはどうかと思うが、実際の釣り上がってくるのだから仕方がない。福島などでソイ、メバルなどを胴つき仕掛けで海底をとんとんやっていると、頻繁に根がかりする。これを強引に引くとやや鈍い感触がして海底を離れ上がってくるのがまさしくマボヤである。マボヤが好きならソイなんて見向きもしないでマボヤ釣りもいいものである。 |
|
|
|
 |
| 根元を切り取り、なかから出てくる海水をとっておく。殻からはずし刺身にすて、海水をまびして単に食べる。これがもっともうまい食べ方だと思う。塩か生醤油で。 |
 |
| 刺身にしょうゆをかけ回し、ご飯にのせる。うまいんだか、まずいんだかわからないのだけど、ときどき食べたくなる。宮城県を旅しているときに目撃したもの。 |
 |
| 殻ごとゆでると面白い味わいになる。食感が変わり、旨味が濃厚になる。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
関連コンテンツ
Copyright©2025 Bouz-Konnyaku All Rights Reserved.







 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典




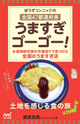

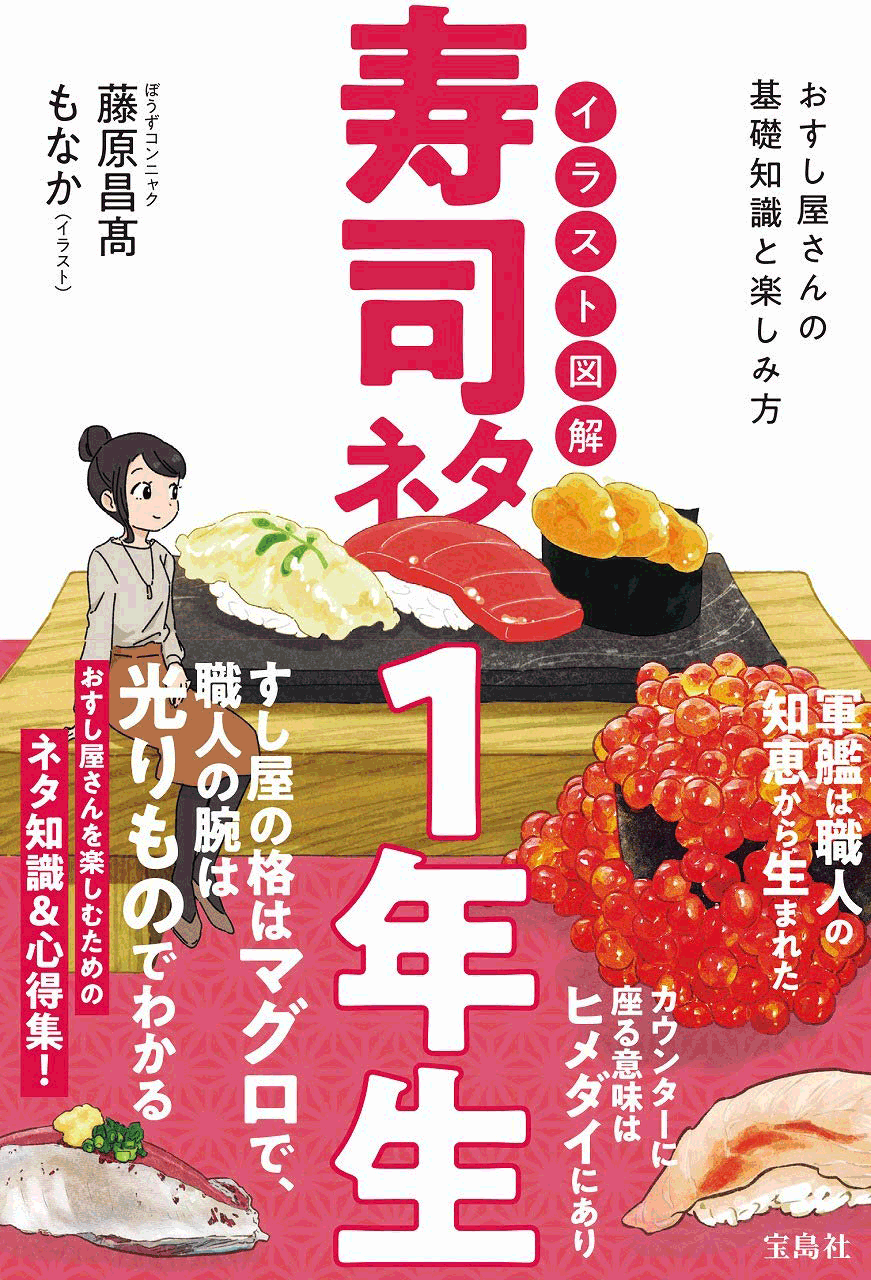 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生



