 ここ2回の新潟行では、2回とも、帰宅した日の夜中は「サケのあらのみそ汁」を作っている。
ここ2回の新潟行では、2回とも、帰宅した日の夜中は「サケのあらのみそ汁」を作っている。簡単に作れるし、腹にたまるからだ。
ついでにいうと酒の肴にもなる。
濃い目に作るのが疲れているのに眠れないときの味つけの秘訣だ。
暑い日でも寒い日でも、熱々を食べることにしている。
サケの魅力は骨などからいいだしが出ること。
煮ても硬くならず、身離れがよくふんわりとして甘味があることだ。
そしてサケ科特有の風味が感じられることもいい。
これ以上望めないくらいに味わい深く、酒と一緒に流し込むと味の相乗効果を生む。
酒は新潟県新潟市内野町「鶴の友 特撰」を正一合。
コラムの続きを読む
 新潟県胎内市中条町の昼ご飯は、朝市のバアチャンおすすめの『福よせ食堂』で。
新潟県胎内市中条町の昼ご飯は、朝市のバアチャンおすすめの『福よせ食堂』で。いちばんのおすすめは朝市の通りの『志まつ』というジンギスカンの店だったが、「行列ができる」、「肉肉しすぎる」ので御免被る。
昨日の夕方からタイの刺身とサツマイモの天ぷら1切れしか食べていないので、危険を感じるくらいにお腹が空いている。
昔ながらのサンプルのある店先に立ち、オムライスだと決めて入る。
店の中が比較的明るいのがいい。
店員さんも親切そうだし、じっくり考えてお願いしようと思ったら、だんだんオムライスの陰が薄くなる。
食堂のチャーハンもいい、気がする。
考えてみると食堂で焼きそばもある。
焼きそばにしようと思ったら、中華丼なんて何十年も食べていないことに気づく。
考えた挙げ句にとどのつまりの、カツ丼セットにする。
ラーメンとのセットは珍しい気がする。
やや甘めのカツ丼がはらわたにしみ通る、秋の昼なのであった。
喉を通ると同時に胃で消化されていくのを感じる。
醤油ラーメンは食堂にしては鶏ガラの香り少なく、なんのスープなんだろう? とか考えたり、あれ、新潟県の「なると」はこんな「なると」だっけな、富山のような個性的な「なると」ではないなどと考えたり。
考えに考えている内にたくわん一切れだけが寂しく残る。
食堂の隅、たくわん一切れ食べる、おのこありける。
コラムの続きを読む
 10月17日、神奈川県小田原魚市場、二宮定置はたいへんなことになっていた。大量の小型のゴマサバ、イサキでダンベ3個、4個が並ぶ。
10月17日、神奈川県小田原魚市場、二宮定置はたいへんなことになっていた。大量の小型のゴマサバ、イサキでダンベ3個、4個が並ぶ。そんな慌ただしい中、お邪魔して申し訳ない。
中に小型のタカベがあった。
体長13cm・38g前後である。
高級魚のタカベだが、このサイズではどうしようもない。
以上は前回にも書いた。
これで干ものを作る。
水洗いして水分をきり、塩水に10〜15分ほどつける。
室温20℃前後で塩分を控えているなら10分くらい。
水分をよくきり、室内の風通しのいいところで24時間干す。
地域によっては外干しができる。
この場合、半日くらいで干し上がる。
後は焼くだけである。
非常に強いうま味があるのだけれど、表面にまず脂の熱せられ、また固まる途中の半溶けの風味がする。
他の魚にはない独特の風味で、これがタカベの価値を上げているのだ。
皮も身も全部うまいのが小型魚の干もののいいところだ。
蒸かしたサツマイモのお菜にする。
滋賀県の番茶を大ジョッキで1パイ。
コラムの続きを読む
 道具話はだいたいにおいて独りよがり的なものとなってしまう。
道具話はだいたいにおいて独りよがり的なものとなってしまう。意見が違っても悪しからず。
我ながら呆れるくらい、二枚貝の料理・刺身が大大、大好きだ。
バカガイ(青柳)、トリガイ、アカガイ、ウバガイ(ほっきがい)などなどいいものがあると必ず手が伸びる。
ちなみにホタテガイの話は別項を立てる。
当然、貝剥きほど使用頻度の高い道具はない、といった感じだ。
寒くなると殻つきマガキが中心になるが、食べる頻度が高いので、貝剥きは出しっぱなし状態になる。
我が家にある貝剥きの数はわからない。
20本以上ある可能性が高いが、バラバラに散らばっているのでどこにあるのかわからない。
意外にもらいものが多いし、仕方なく通販でカキの類を買うと、メチャクチャ使いにくい貝剥きが大きなお世話なのについてきたりする。
コラムの続きを読む
 金曜日は福島県から持ち帰った水産生物と産物の整理で費えた。
金曜日は福島県から持ち帰った水産生物と産物の整理で費えた。土曜日は旅の疲れに、産物整理・生物の同定(種を割り出す作業)の疲れの二重奏でなにがなんだかわからない日だった。
日曜日、窓を開けるとやけに風が冷たく、まさに鍋日和だ。
水産物が底をついたときで、たまには魚を食べない日があってもいいだろうと思ったものの、なんだか寂しくなって近所のスーパーまで鍋材料を買いに行く。
驚くほど魚がなかった。
養殖魚ばかりなのは海が荒れているせいだろう。
目的の北海道産マダラの切り身はあったにはあったが1パックだけ。
塩ダラ(「ぶわたら」ともいい塩蔵したマダラ)がなく、残っていたのは生(塩をしていない)タラである。
さて、福島県相馬市で今季初めて白菜を買った。
新潟県胎内市中条で文化鍋(ふた付き両手のアルミ鍋)を買った。
これで鍋を作る。
マダラは食べやすい大きさに切る。
振り塩をして少し寝かせて湯に通して氷水に落とし、表面のぬめりを流し水分を切る。
白菜など野菜は食べやすい大きさに切る。
高知県の酢みかんは黄色くなってしまっているので香りは少ないものの、果汁はたっぷり絞れるので、たっぷり切る。
鍋にソウダ節でとっただし半分、水半分を合わせて塩と酒で味つけする。
後は煮ながら食べるだけだ。
マダラの切り身は手に入れやすく、しかもハズレがない。
関東では至って日常的なタラだが、鍋ものにすると最強だと思う。
煮えたタラは矢鱈においしい。
身は層をなしており非常に柔らかく脆弱で甘味と魚ならではのうま味がある。
白菜は日数の少ない品種(白菜は品種名+結球までの日数で、今あるものは夏撒き)だと思うが、久しぶりに食べるとうまいな。
魚、野菜、豆腐など多様で量食べられるのも鍋のよさだ。
酒は福島県二本松市の「千功成 本醸造」(檜物屋酒造店)。
名前はボク好みではないが、味はボク好み。
コラムの続きを読む
 高知県土佐市、白木果樹園からいろんな種類の柑橘類を送ってもらった。
高知県土佐市、白木果樹園からいろんな種類の柑橘類を送ってもらった。現在整理中だけど、非常に難航している。
とりあえず、1種ずつ紹介していきたい。
今回はピンクレモネードだ。
アメリカで作られているユーレカレモンという、たぶんレモンの1種らしいものから、アメリカで生まれた変種らしい。
酢みかんでレモネードとあると、少し甘味があるという意味だと勝手に解釈しているが、このピンクレモネードも少し甘い。
スダチのような渋酸っぱいというのではなく、甘味があって、渋味は少ない。
香りはそれほど強くない。
レモン同様に焼きものにソテーしたものに、刺身などにも使えるが、いちばんいいな、と思ったのはカルパッチョだ。
穏やかな甘さが、オリーブオイル、にんにく、塩と融合して味の一部と化して邪魔しない。
魚の薄い切り身のうま味の中に酸っぱい甘さが感じられる。
皮ごと飾ると皮の縞々模様とピンク色の果肉が映える。
もっと意外だったのは、ハナザメのステーキに使ったときの酸っぱい中のまろみである。
醤油やバターとの相性がいいようだ。
コラムの続きを読む
 宿毛市、すくも湾漁協中央市場の入り口で、とても魅力的な赤い提灯を発見した。
宿毛市、すくも湾漁協中央市場の入り口で、とても魅力的な赤い提灯を発見した。大判焼きである。
ボクは甘いもの好きであるが、大判焼き、今川焼き、鯛焼きは自分を失うくらい好きだ。
きっとサッポロビールの柴田さんは驚いたと思うけど、何が何でも大判焼きだ、と脳みそに一億個くらい大判焼きの文字が蠢いて、他のものが入り込む余地がなくなってしまった。
買ってうれしいのは大判焼きの温かさだ。
達磨の絵が焼き付けてあり、「すくも」とある。
コラムの続きを読む
 胎内市中条の朝市は、3のつく日と、8のつく日の開かれるので三八市である。
胎内市中条の朝市は、3のつく日と、8のつく日の開かれるので三八市である。大方見終わろうとしているとき、「9時になったら魚屋が来るから待ってな(意訳)」と言われた。
少し町を見て帰ってきたら、有名だという焼き肉店の前にライトバンがとまっていた。
コラムの続きを読む

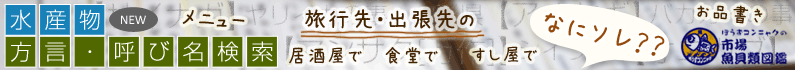

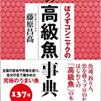 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
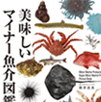
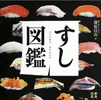
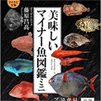
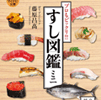

 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生




























