 ニュースでは、なぜクマが人の住む領域に侵入してくるのか、を報道しない。
ニュースでは、なぜクマが人の住む領域に侵入してくるのか、を報道しない。個人的には、クマが人の領域にくるのは、無闇に人の住む領域を増やしていること。
クマのすむ領域にエサ(ご飯)がないためじゃないかな?
秋田県知事がやろうとしていることは、わからないでもないが、片手落ち(差別用語だけど)だと思うな。
例えば環境省や国土交通省(?)がやらなければいけないことは、野山川海の現状を把握し、できるだけ人間の領域を減らし、クマの領域をお腹いっぱいになるくらいのエサ(ご飯)が増える環境にすることじゃないかな?
江戸時代の書籍を読みあさっているけど、空腹、飢餓ほど残酷なものはないようだ。
クマもたまらないと思う。
われわれ至って無知な普通の人間もこれを機会に考えるべきかも。
コラムの続きを読む
 高知県で飲まれているお茶は種々様々である。
高知県で飲まれているお茶は種々様々である。茶といってもマメ科植物の茶あり、所謂茶であるチャノキの茶もある。
もっとも一般的なのは土佐番茶といわれるものらしい。
チャノキの茶を焙じたものと、きし豆(カワラケツメイ)の葉を焙じたものを混ぜたもの。
安芸市や黒潮町の直売所で買ったものは、きし豆(カワラケツメイ)の比率が多く、甘味がある。
高知県高知市帯屋町『森木翠香園』のものはチャノキの葉が多めで、きし豆が少ない。
コラムの続きを読む
 午後2時過ぎに新潟市に戻る。
午後2時過ぎに新潟市に戻る。昨夜から睡眠時間2時間弱なので、この時間帯に疲れの大波が来る、
ここで眠ってしまうと体が余計にだるくなるの予定通りに銭湯に行く。
新潟市東区秋葉通にある小松湯は驚くなかれ、午前8時半からやっている。
最近、ボク好みの普通の銭湯が全国的に消えてしまいつつある中、新潟市内には10店舗近くある。
新潟市は銭湯のある町と言ってもいいだろう。
小松湯は昔ながらの設備の、昔ながらの銭湯である。
シャワーが出なくて困っていたら、「開けたり閉じたりすると出るから(身振りで)」と教えてくれる。
常連さんが優しいのがいい。
じっくりゆっくりと湯船に浸かり、ジェットを背中に受けて上がったら、体がクラゲ状態になっていた。
ぼうずコンニャクなのでコンニャク状態かも。
コラムの続きを読む
 毎年、日本海のズワイガニの11月の解禁後に、高級な日本海の雄ガニは1尾だけ11月中に買うことにしている。
毎年、日本海のズワイガニの11月の解禁後に、高級な日本海の雄ガニは1尾だけ11月中に買うことにしている。今年は解禁が1ヶ月早い山形県産を買ってみた。
日本海産雄のズワイガニは年1回だけの贅沢である。
12月になるととても手が出なくなる、その前。2024年は鳥取県産、2023年は兵庫県産、そして今年が山形県となる。
余談だが、山形県では「芳ガニ」と呼ばせたいらしい。
「芳」は当て字で、山形県から能登半島にかけて「葦ガニ(よしがに)」と呼ばれていた。
足が長く細いので「葦(ヨシ)」なのだろう。
「よしがに」という消え去りそうな呼び名が復活するのはいいことかも。
さて、鼠ヶ関から来たズワイガニはとても身が詰まっていた。
甘味が強くカニらしい風味も豊かだ。
日本海どころか、太平洋側、北海道のズワイガニと比較する能力すら持ち合わせていないが、今季初ズワイガニはボクをとても幸せな気分にしてくれた。
ズワイガニの身の魅力は筋肉が束状になっていて、ヒモ状にほぐれることだ。
脚1本だけ味見するつもりが、昼下がりなのに2本、3本とやめられなくなる。
あっと言う間に鉗脚(ハサミ脚)も含めて食べきる。
コラムの続きを読む
 ここ2回の新潟行では、2回とも、帰宅した日の夜中は「サケのあらのみそ汁」を作っている。
ここ2回の新潟行では、2回とも、帰宅した日の夜中は「サケのあらのみそ汁」を作っている。簡単に作れるし、腹にたまるからだ。
ついでにいうと酒の肴にもなる。
濃い目に作るのが疲れているのに眠れないときの味つけの秘訣だ。
暑い日でも寒い日でも、熱々を食べることにしている。
サケの魅力は骨などからいいだしが出ること。
煮ても硬くならず、身離れがよくふんわりとして甘味があることだ。
そしてサケ科特有の風味が感じられることもいい。
これ以上望めないくらいに味わい深く、酒と一緒に流し込むと味の相乗効果を生む。
酒は新潟県新潟市内野町「鶴の友 特撰」を正一合。
コラムの続きを読む
 新潟県胎内市中条町の昼ご飯は、朝市のバアチャンおすすめの『福よせ食堂』で。
新潟県胎内市中条町の昼ご飯は、朝市のバアチャンおすすめの『福よせ食堂』で。いちばんのおすすめは朝市の通りの『志まつ』というジンギスカンの店だったが、「行列ができる」、「肉肉しすぎる」ので御免被る。
昨日の夕方からタイの刺身とサツマイモの天ぷら1切れしか食べていないので、危険を感じるくらいにお腹が空いている。
昔ながらのサンプルのある店先に立ち、オムライスだと決めて入る。
店の中が比較的明るいのがいい。
店員さんも親切そうだし、じっくり考えてお願いしようと思ったら、だんだんオムライスの陰が薄くなる。
食堂のチャーハンもいい、気がする。
考えてみると食堂で焼きそばもある。
焼きそばにしようと思ったら、中華丼なんて何十年も食べていないことに気づく。
考えた挙げ句にとどのつまりの、カツ丼セットにする。
ラーメンとのセットは珍しい気がする。
やや甘めのカツ丼がはらわたにしみ通る、秋の昼なのであった。
喉を通ると同時に胃で消化されていくのを感じる。
醤油ラーメンは食堂にしては鶏ガラの香り少なく、なんのスープなんだろう? とか考えたり、あれ、新潟県の「なると」はこんな「なると」だっけな、富山のような個性的な「なると」ではないなどと考えたり。
考えに考えている内にたくわん一切れだけが寂しく残る。
食堂の隅、たくわん一切れ食べる、おのこありける。
コラムの続きを読む
 10月17日、神奈川県小田原魚市場、二宮定置はたいへんなことになっていた。大量の小型のゴマサバ、イサキでダンベ3個、4個が並ぶ。
10月17日、神奈川県小田原魚市場、二宮定置はたいへんなことになっていた。大量の小型のゴマサバ、イサキでダンベ3個、4個が並ぶ。そんな慌ただしい中、お邪魔して申し訳ない。
中に小型のタカベがあった。
体長13cm・38g前後である。
高級魚のタカベだが、このサイズではどうしようもない。
以上は前回にも書いた。
これで干ものを作る。
水洗いして水分をきり、塩水に10〜15分ほどつける。
室温20℃前後で塩分を控えているなら10分くらい。
水分をよくきり、室内の風通しのいいところで24時間干す。
地域によっては外干しができる。
この場合、半日くらいで干し上がる。
後は焼くだけである。
非常に強いうま味があるのだけれど、表面にまず脂の熱せられ、また固まる途中の半溶けの風味がする。
他の魚にはない独特の風味で、これがタカベの価値を上げているのだ。
皮も身も全部うまいのが小型魚の干もののいいところだ。
蒸かしたサツマイモのお菜にする。
滋賀県の番茶を大ジョッキで1パイ。
コラムの続きを読む
 道具話はだいたいにおいて独りよがり的なものとなってしまう。
道具話はだいたいにおいて独りよがり的なものとなってしまう。意見が違っても悪しからず。
我ながら呆れるくらい、二枚貝の料理・刺身が大大、大好きだ。
バカガイ(青柳)、トリガイ、アカガイ、ウバガイ(ほっきがい)などなどいいものがあると必ず手が伸びる。
ちなみにホタテガイの話は別項を立てる。
当然、貝剥きほど使用頻度の高い道具はない、といった感じだ。
寒くなると殻つきマガキが中心になるが、食べる頻度が高いので、貝剥きは出しっぱなし状態になる。
我が家にある貝剥きの数はわからない。
20本以上ある可能性が高いが、バラバラに散らばっているのでどこにあるのかわからない。
意外にもらいものが多いし、仕方なく通販でカキの類を買うと、メチャクチャ使いにくい貝剥きが大きなお世話なのについてきたりする。
コラムの続きを読む

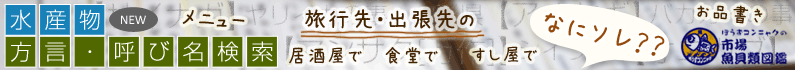

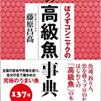 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
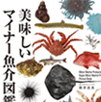
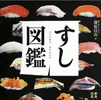
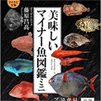
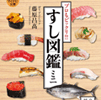

 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生




























