突然とれ始めた深刻な未利用魚、カタボシイワシ
ニシンに似た平凡な姿だけど謎だらけ

カタボシイワシ

未利用魚、未利用魚と騒がしいが、本当に未利用魚といえる魚はほとんどいない。最大の問題点は未利用魚の定義が曖昧なことだ。未利用というよりもお金にならない魚、やっかいな魚は存在する。未利用魚というよりも、問題のある魚とすべきだろう。
魚類を調べ始めたときの、魚類学事始めは魚類図鑑を暗記することだった。そこから人と関わりのない魚を捨てる作業をしたが、カタボシイワシは捨てたことすらおぼえていなかった。国内では非常に影の薄い存在でしかなかった。
鹿児島県南さつま市笠沙の漁師で魚類学者の伊東正英くんから2005年に「突然、大量にとれ始めたんです」といって、送られてくるまで、魚類検索の絵でしかなかった。
1955年の『魚類の形態と検索』(松原喜代松 岩崎書店 1955)に新称とあるが、このときの個体は標本として残っていない。1955年なので、いまだに1945年以前の標本である可能性があり、台湾の個体である可能性も捨てきれない。とすると、南さつま市笠沙で見つかった個体が、国内海域初の個体である可能性もある。
カタボシイワシはニシンの仲間(ニシン目ニシン科サッパ属)でニシンに似ているが、触るとニシンより左右に平たく、体がニシンよりも硬い。カタボシイワシなどサッパ属の特徴は魚の体の底部分に棘のある鱗が並んでいることだが、この部分がとても刺々しい。
インド洋、インドネシアからオーストラリアと生息域の広い魚である。国内では1955年以前には標準和名がなかった。
これが2012年には相模湾にも現れ、2021年には千葉県鴨川市でも見つかっている。
ちなみに、2005年前後に鹿児島県に現れる以前、1900年から2000年にかけて国内では採取されていなかったようだ。(『千葉県から得られた分布東限記録のニシン科魚類カタボシイワシ』畑晴陵 、佐土哲也、中江雅典)。
この謎だらけの魚が国内で大量に揚がるとどうなるか? すでに見つかって20年以上になるのに流通上ではほとんど見ることがないのだ。
かといって無視できる量ではない。
他の魚に混ざる程度ならいいが、トン単位で未知の魚が揚がるととてもやっかいである。ほぼ魚粉などになり、直接人の口に入らないという意味で2025年現在明らかに未利用魚である。
瀬戸内海のヒラ同様に薄切りの刺身にする

カタボシイワシの刺身

水産物の水揚げが極端に減っているとき、なので相模湾などでとれた個体で料理法を模索している。
同じサッパ属には岡山県で「ままかり(飯借り)」と呼ばれているサッパがいる。サッパ同様に身はとても味のいい魚なのだ。
おいしい魚なのに食べ方がわからないので廃棄されていると言う点で、瀬戸内海のヒラにも境遇が似ている。
ヒラと同様に体に無数の長い小骨がある。また先にも述べたように体の基底部分に強い棘のある鱗が並んでいる。
この難点を取り除くことから料理は始まる。
刺身は、まずは頭部を落として、この棘のある鱗の部分を切り落とす。三枚に下ろして瀬戸内海のヒラ同様に薄切りにしていくのである。
身には強いうま味があり、時季によっては豊かな脂がある。要するに薄切りの刺身は絶品なのである。










 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典




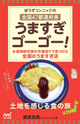

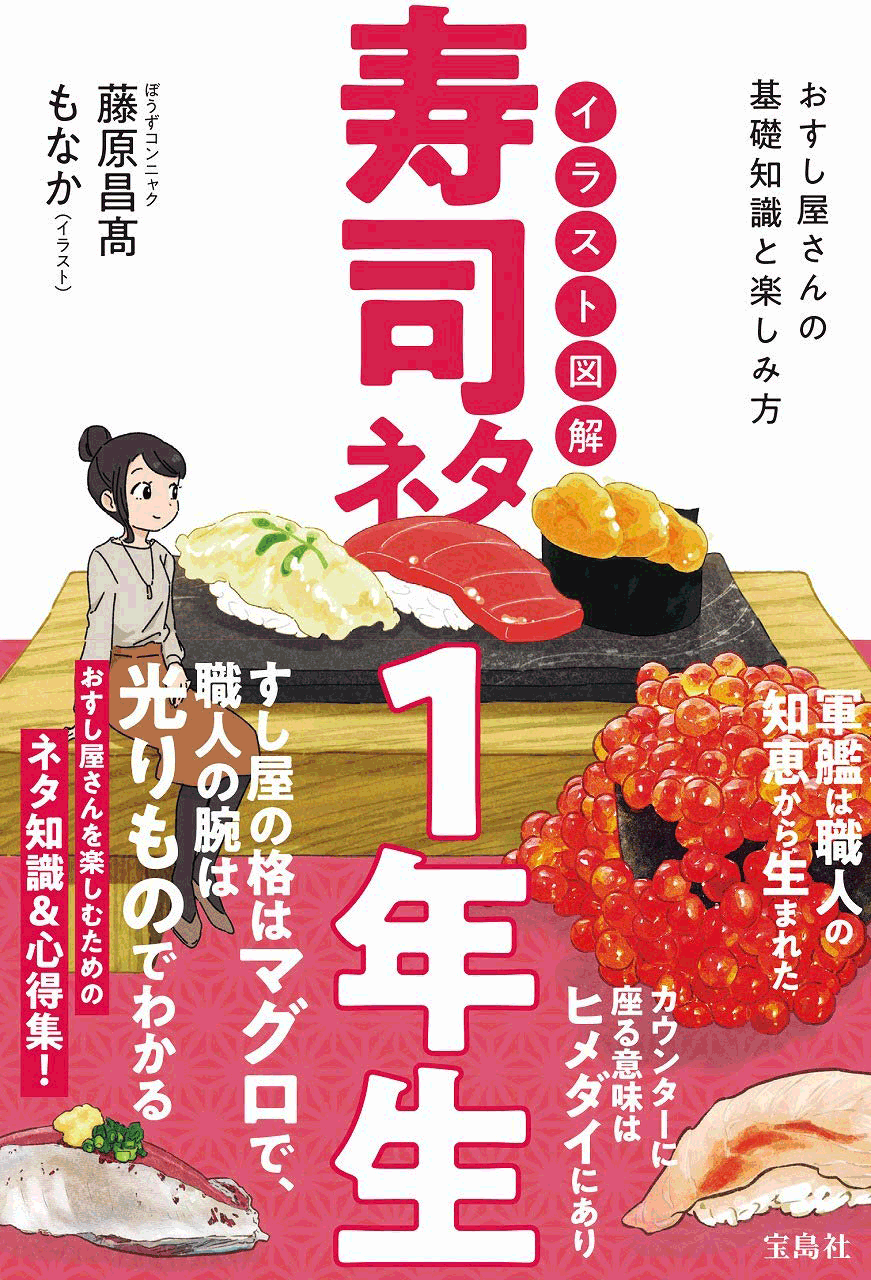 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生



