ほとんどの地域で価値が低すぎる、コノシロ
都市が隣接する内湾に多く、味がいいのに食べる地域が少ない


コノシロは北海道南部から九州までの汽水域や内湾に生息している。内湾にたまった泥を飲み込み、中にいる珪藻や甲殻類などを食べている。
「子代」という漢字を当てることがある。下野に住んでいた娘と有間皇子(ありまのみこ。孝徳天皇の悲劇の皇子。640年-658年)が登場するわざとらしい話があるなど、話題豊富な魚である。
大都市圏のある内湾域に多い魚なので知名度は高い。古くからの共通固有名詞があるので、なんらかの形で古代に流通していたはずである。
この魚の問題点は食べる地域が狭すぎるということだ。
関東では全長20cmくらいまではすし種に使うが、それ以上になると流通量がぐっと減り、最底辺の価格帯になる。
当然、産地で水揚げされても廃棄(フィッシュミール)などになることが多い。
■写真は全長25cm以上の「このしろサイズ」のコノシロ。
世界一高いのは稚魚期だけ、後は捨て値


横道にそれるが5月後半の新子(コノシロの稚魚)の走りは、豊洲の仲買の話では最高値で100gあたり2万円はする。
1gほどの稚魚なので1尾、200円くらいはするが、この値をつけるのは東京ならではの見栄である。ちなみに熟練の職人でも100g、100尾をロスなく下ろすのは難しいと思う。しかもこのサイズだと1個の握りずしに20尾はいる。
100gあたり1万円のは何度か購入しているが、クロマグロのようにご祝儀相場ではなく、連続して高値をつけることなどから世界一高い魚でもある。
最近は全長12cmくらいのもっとも安かったはずの「こはだサイズ」の、鮮度のいいものもやけに高い。超高級魚である。
それが全長20cmを境に、すし屋に見向きもされなくなるのだから謎である。
■写真は100g1万円の新子。
大きなサイズが安いのが大問題なのである


コノシロは東日本よりも、西日本の方が食べている地域が広い。取り分け日常的によく食べているのは熊本県だ。
また瀬戸内海でも比較的よく食べているが、岡山県などのようにある程度食べていた地域でもコノシロの消費は減っている。岡山県特有の、小型定置のコノシロの値段は下降傾向が止まらない。
コノシロは小さいほど値段が高いが、大きいほどおいしい。大きいほどうま味成分が多いと思っている。
この大きいコノシロのおいしさをいちばん知っているのは熊本県、特に天草地方である。
大阪名物、「ばってら」は今ではマサバの押しずしだが、大阪市内順慶町(現中央区南船場順慶町通に名を残す)「うお常(福島にある中央市場に移転していたが廃業)」の店主が明治26年(1893年)に考案したもので、もともとの材料は食べないので激安だったコノシロだった。コノシロの姿ずしが小舟(ポルトガル語でバッテーラ)の形に似ているので「ばってら」になったとされている。
ただこの話はかなり怪しい。なぜなら熊本県天草に姿ずしがあり、たぶん同じものだからだ。「大阪人はこじつけが好き」、とは雑喉場研究で有名な故、酒井亮介先生が言われたことだ。
■写真は熊本県天草の姿ずし。
熊本市で何気なく食べた刺身に大感激したことがある


熊本県では姿ずしにもするし、刺身でも食べる。刺身は熊本市内の食堂でも食べられた。
コノシロの成魚の刺身くらいおいしいものはない。
江戸前ずし店では「コノシロは使えねー」などと見向きもしないが、実は酢締めにしてもびっくりするほど美味である。
■写真は熊本県熊本市の食堂で食べた、コノシロの刺身。










 ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典
ぼうずコンニャクの日本の高級魚事典




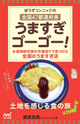

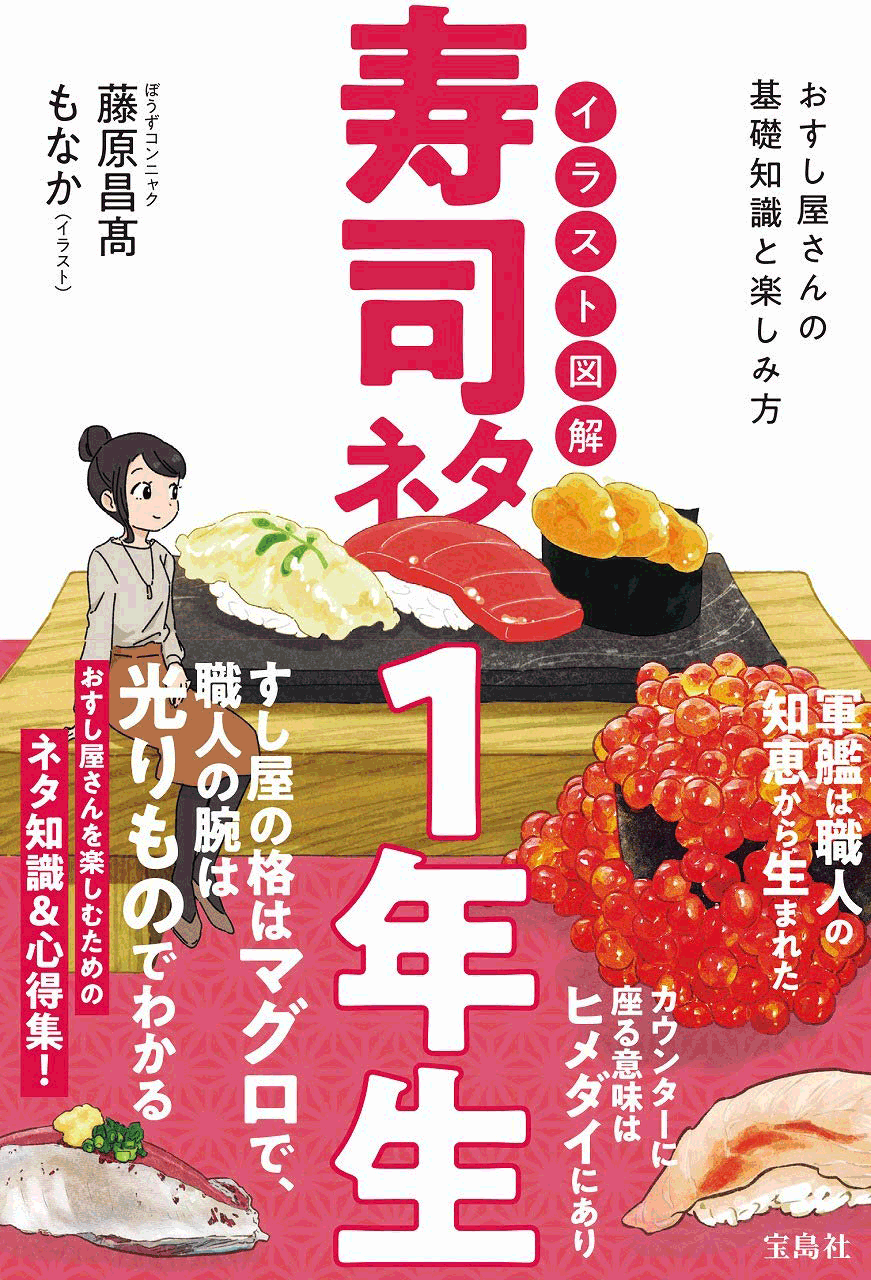 イラスト図解 寿司ネタ1年生
イラスト図解 寿司ネタ1年生



